
【竹取物語】「かぐや姫」のお話は中国起源!・・・・・・かもしれない【嫦娥奔月】
-
 japanchinaGEO
japanchinaGEO
- 39602
- 6
- 36
- 1
嫦娥(じょうが、こうが)は、中国神話に登場する人物。后羿の妻。古くは姮娥(こうが)と表記された。
『淮南子』覧冥訓によれば、もとは仙女だったが地上に下りた際に不死でなくなったため、夫の后羿が西王母からもらい受けた不死の薬を盗んで飲み、月(広寒宮)に逃げ、蝦蟇(ヒキガエル)になったと伝えられる。
別の話では、后羿が離れ離れになった嫦娥をより近くで見るために月に向かって供え物をしたのが、月見の由来だとも伝えている。
中国人にとっては月の模様は蛙の形!?
中国人の中には月の模様は兔ではなく蛙の形だと言う人がいたりする。
兎のほか、古代中国では月にはヒキガエル(蟾蜍、せんじょ)が棲んでいるとされていた。中国で古くに製作された模様の中には、月にいるものとして兎とヒキガエルを同じ画面内に収めて登場させているものも見られる。
この「ヒキガエル」が転じて「兎」になったのではないか、という説もある。これは、ヒキガエルを意味する「顧菟」の「菟」字が「兎」と誤って認識されてそのまま定着したのではないかというものである。
不死の薬は実は『竹取物語』にも登場
嫦娥は「不死の薬」を盗み、月へと逃走していくが、実は「不死の薬」は『竹取物語』の終わりの部分にも登場している。
かの奉る不死の薬に、また、壺具して、御使ひに賜はす。勅使には、つきの岩笠(いはかさ)といふ人を召して、駿河の国にあなる山の頂に持てつくべき由仰せたまふ。嶺(みね)にてすべきやう教へさせたまふ。御文、不死の薬の壺並べて、火をつけて燃やすべき由仰せたまふ。その由承りて、つはものどもあまた具して山へ登りけるよりなむ、その山をふじの山とは名づけける。その煙(けぶり)いまだ雲の中へ立ち上るとぞ言ひ伝へたる。
【現代語訳】かぐや姫が献上した不死の薬に、また壺を添えて、御使いの者にお渡しになった。勅使に対し、つきの岩笠という人を召して、駿河の国にあるという山の頂上に持っていくようお命じになった。そして、山の頂でなすべきことをお教えあそばした。すなわち、お手紙と不死の薬の壺を並べ、火をつけて燃やすようにとお命じになった。その旨をお聞きし、兵士らを大勢連れて山に登ったことから、実はその山を「富士の山(士に富む山)」と名づけたという。そのお手紙と壺を焼いた煙が今も雲の中へ立ち上っていると言い伝えている。
もちろん、これらを以て『竹取物語』が中国起源だとするのは無理があるかもしれない。「月と不死」を連想させる説話は日本と中国以外にも色々と存在するのである。
しかし、『竹取物語』と「嫦娥奔月」の神話とに何らかの関わりがある可能性は十分にあるのではないだろうか?
 GEO ジオ@中国古典オタク
@japanchinaGEO
GEO ジオ@中国古典オタク
@japanchinaGEO
だいたいこんな感じの話が伊藤清司先生の『かぐや姫の誕生』に書いてあった。 #かぐや姫の物語 伊藤清司のかぐや姫の誕生―古代説話の起源 amazon.co.jp/gp/product/406… … pic.twitter.com/M0HWrDI433
2015-03-13 23:07:09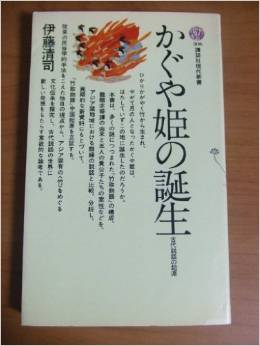 拡大
拡大
これが火鼠のかわごろも?火で洗う布「火浣布」
 GEO ジオ@中国古典オタク
@japanchinaGEO
GEO ジオ@中国古典オタク
@japanchinaGEO
なお、かぐや姫が出す無理難題の一つ、「火にくべても燃えない布」は中国の説話に出て来る「火浣布」だと言われる。「火浣布」は「火の中に入れることによって洗える布」なので、「火にくべても燃えない布」なわけだ。 %かぐや姫の物語
2015-03-13 23:18:368巻本『捜神記』には次のように記載されている。
「漢世西域舊獻此布,中閒久絕。至魏初時,人疑其無有。文帝以為火性酷裂,無含生之氣,著之典論,明其不然之事,絕智者之聽。及明帝立,詔三公曰:「先帝昔著典論,不朽之格言,其刊石於廟門之外及太學,與「石經」並以永示來世。」至是,西域使人獻「火浣布」袈裟,於是刊滅此論,而天下笑之。」
火の中に入れても燃えないという「火浣布」であるが、『三国志』の魏の初代皇帝・文帝・曹丕はそんなものはありえないとして、それを著書『典論』に記した。しかし、次の明帝の時代に西域から「火浣布」の実物が献上され、天下の人々は曹丕を笑ったという。
最後にネットで読める「斑竹姑娘」に関する研究にはどんなものがあるの?
「斑竹姑娘」に関するネット上で読める学術論文としては次のようなものがあります。興味がある方は一度読んでみるといいかも?